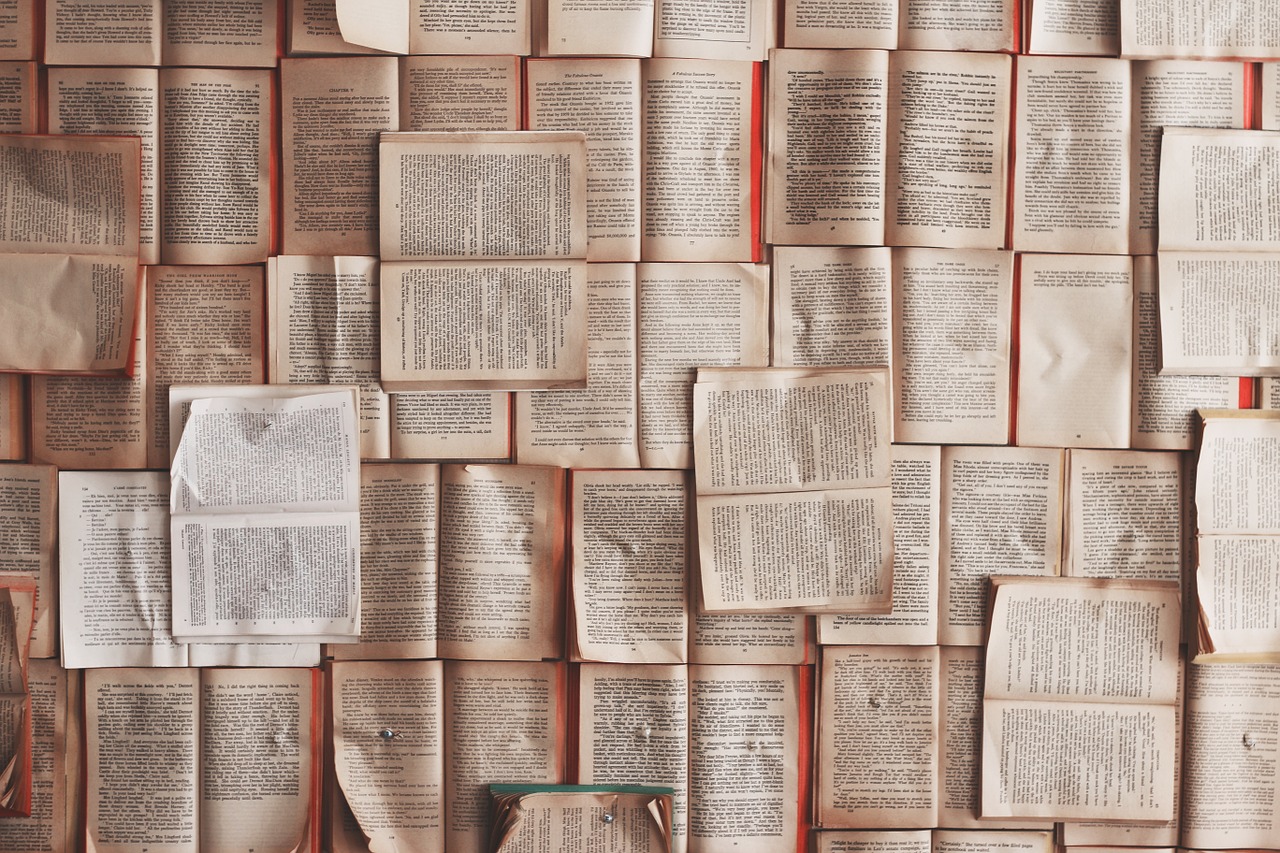このブログの読者は何を読んだのでしょう。上位20冊をご紹介。
第20位:わかったつもり 読解力がつかない本当の原因
[amazon_link asins=’B00GU4R8YQ’ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’d21055bd-a8d5-4737-a44a-72384eaf290f’]
読解力をつけたいと思って読んだ本でしたが、世の中には同じように思う人がいる、ということでしょうか。
「わかったつもり」になりがちだと思う人は、おすすめです。
第19位:グロービスMBAマネジメント・ブック
[amazon_link asins=’447800496X’ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’73af7808-6db3-43ee-bd46-c97c2337a06f’]
有名なグロービスMBAシリーズ。本書は経営マネジメント全般をカバーした本で、最初に読むにはおすすめ。マーケティング、ファイナンス、組織など、マネジメントとはどういう範囲なのかを扱うのかを理解できます。
グロービスといえば、最近テクノロジーにフォーカスしたクラスを開講してましたね。テクノロジーは本当に重要なウェイトになっているので、良いと思います。
第18位:ファスト&スロー(上) あなたの意思はどのように決まるか?
[amazon_link asins=’B0716S2Z29′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’e30dedba-683b-42d4-9fc3-a7b4f6b9d21c’]
ノーベル経済学賞を獲得したダニエル・カーネマンの有名な本です。
行動経済学というのは広く浸透してきましたが、この重厚な本は、人の心理がどのように作用し、行動に結びつくかを様々な事例を元に紹介してくれます。
第17位:全史×成功事例で読む 「マーケティング」大全
[amazon_link asins=’4761270233′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’99184f0b-eede-4ecb-b010-c0194af496ae’]
マーケティングの発展の歴史を眺めながら、マーケティング手法を学べる一冊。
市場が成熟するに従って、マーケティングの重要性は高まっていますので、歴史からおさらいをどうぞ。
第16位:入門経済学
[amazon_link asins=’4535558175′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’7e0d5e3a-2b35-4609-ad48-575f517ed4ec’]
経済学というのはとっつきづらいものではありますし、この真面目な教科書が売れていることが少し不思議ではあります。しかし、本書はとても平易に経済学の理論が書かれているので、しっかり学びたい人にはおすすめです。
第15位:ストーリーとしての競争戦略 ―優れた戦略の条件
[amazon_link asins=’4492532706′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’109aa958-cc6f-43a5-a873-6a96d41a0a61′]
経営戦略としては、未だに色褪せない名著。時々読み返すと、また発見があるから不思議です。
第14位:イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」
[amazon_link asins=’4862760856′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’a439d55b-b5b5-4ca9-814a-0cabc2963354′]
こちらも2010年発売ですが、未だに売れる濃厚な一冊ですね。課題解決としての原則がわかりやすく書かれてます。
第13位:ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現
[amazon_link asins=’4862762263′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’2fc00c9c-84dc-42f6-879c-8343ffd03a0e’]
上半期に読んだ中では、一番印象に残ってる本ですね。組織論の歴史と最新のトレンドが描かれていて、価値観のシフトが起こってるんだなって思いました。
第12位:20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義
[amazon_link asins=’4484101017′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’ac59b45a-e76f-4839-af17-ddd1a468bc19′]
起業家精神を説いた一冊。副業や兼業も注目される中で、自分でビジネスを起こすというのがどういうものか、考える良いきっかけになるんじゃないでしょうか。
第11位:リーン・スタートアップ
[amazon_link asins=’4822248976′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’91e5d7dd-fc61-4a30-bd1e-3e0785807079′]
起業へのハードルはどんどん下がっていますが、その中でどういうアプローチをとるべきかを学ぶには、この本が良いでしょう。
第10位:グロービスMBAマーケティング
[amazon_link asins=’B07MTP7DZ5′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’be222db4-bf23-4a96-ab54-3fa7dac66c40′]
19位にも登場したグロービスのMBAシリーズ。こちらはマーケティングの本です。
第9位:ドラッカーが教える実践マーケティング戦略
[amazon_link asins=’4862802419′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’3f1165dd-2386-4597-9676-c1bab8603573′]
ドラッカーシリーズはたくさんありますが、この本は読みやすいのが特徴。
第8位:ざっくり分かるファイナンス
[amazon_link asins=’B00GU4R7QA’ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’795e35df-f977-4c6e-82bf-a28fc90e847e’]
「ファイナンス」という言葉の意味がよくわからない、会計との違いを知りたいという方におすすめ。
第7位:知識創造企業
[amazon_link asins=’4492520813′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’66e42164-e951-4a5d-b781-1f6a73bd3601′]
情報化社会という言葉が古くなったぐらい、情報があふれていますが、組織が情報を使いこなして強い組織になるためには、ナレッジマネジメントが重要になります。ナレッジマネジメントの教科書ともいえる本書は、今でも売れていますね。
第6位:財務3表一体理解法
[amazon_link asins=’4022736844′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’7c3f7f82-c3b6-453b-9d74-a1ae20eaf402′]
財務諸表をどう読むか。基本を学んでも、いまいち起業の全体像が財務諸表からはわからない、という状況が僕にはありました。そのときにこの本を読んで、「なんてわかりやすい表現なんだ」と感心したのを今でも覚えています。
第5位:モチベーション3.0
[amazon_link asins=’4062816199′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’c6b9015d-de88-46a7-aba0-268d4ebca19d’]
2010年に発売された本書が、いまだに売れるのも不思議な気もしますが、確かに名著です。アメとムチという単純な作用では人は動かない、ということ。モチベーションを高めると人の生産性も上がること。人のモチベーションの源泉はどこにあるかを知りましょう。
第4位:財務3表図解分析法
[amazon_link asins=’4022736852′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’c0875061-7605-4a32-b53d-785af2a8b146′]
6位の「財務3表一体理解法」と同じシリーズです。セットでどうぞ。
第3位:この世で一番おもしろいミクロ経済学
[amazon_link asins=’4478013241′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’1f7b97fa-e048-49db-920f-26b9660a95e5′]
経済学は、ミクロ経済学とマクロ経済学に大別されるのですが、主に一般でイメージされるのは「マクロ経済学」でしょう。しかし、ミクロ経済学も企業の取引や経済活動の原理が理解できます。本書は漫画でわかりやすく書かれているので、最初の導入におすすめ。
第2位:この世で一番おもしろいマクロ経済学
[amazon_link asins=’4478017832′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’8a4f8c79-c274-40f3-a768-1ba71489f80c’]
3位にあるミクロ経済学と同じシリーズ。マクロ経済学の方が説明が難しいと思っていましたが、期待を裏切らずわかりやすい説明が漫画表現されています。
第1位:経営戦略全史
[amazon_link asins=’4799313134′ template=’Original’ store=’tob-22′ marketplace=’JP’ link_id=’bab92940-6a9f-4b46-ba09-a130bfe21a33′]
経営戦略と言うジャンルは少しずつ歴史を積み重ねてきたわけですが、それを一冊に丁寧にまとめたのが本書です。一冊持っておくと、教科書的に読み返すことができるでしょう。
以上、2018年上半期売上が多かったビジネス書でした。興味があるジャンルはありましたでしょうか。良い読書を。